院長のひとり言
不妊治療を始めてからの不調〜hCG注射編〜
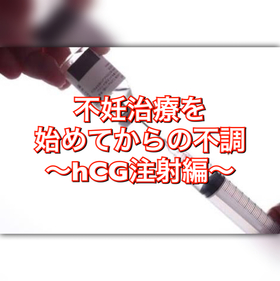
不妊治療を始める前は正常だった基礎体温や多少数値が安定しなかった程度のホルモンバランス。
不妊治療をはじめてから基礎体温表がガタガタになったり、血液検査の結果が乱れてきて注射の回数が増えていくなんて事はありませんか?
卵をつくる、育てる力は本来、皆さんが持っている自己治癒力、妊孕性です。
大切なのはその力を最大限に発揮する環境作り、体作りになります。
それにちょこっと背中を後押ししてあげるのが高度生殖補助医療になるんです。
けれど、それを知らずに不妊治療を初めてしまうと不必要にホルモン治療をしてしまったりします。
結果的に生理周期が短くなったり長くなったりしてしまう事があるんです。
実際に薬の影響なのか、それともストレスなのか、他にも原因があるのか、ドクターに聞いてもイマイチ納得できる回答が得られない場合も多いんですよね。
排卵誘発剤の中でも特にhMG注射の長期使用や必要以上の量を使用した高刺激法の場合、卵巣機能が低下し、結果的にホルモンバランスが乱れることがあります。
卵巣機能が低下するとFSH(卵胞刺激ホルモン)の値が高くなりやすく、卵胞が育ちにくくなってしまいます。
本来、排卵はLHというホルモンの急上昇によって起こります。
ただ、LHというホルモンは人工での合成が難しく、代替としてhCGが使われるんです。
本来のLHの効果は一瞬で、実際に分泌されている時間は30分程とも言われています。
しかし、hCGの効果って体に残ってなかなか消えないんですよね。
その為、体の中にhCGが長く留まり、妊娠した場合の着床過程に影響を及ぼす事も多いんです。
また妊娠しなかった場合、その効果は次周期以降の月経周期にも影響してしまいます。
hCG投与の翌周期には遺残卵胞と呼ばれる少し大きめのホルモン産生嚢腫ができてくることが多くあります。
この遺残卵胞の影響は次に良好な卵子を育てることができなかったり、排卵しないだけでなく、黄体機能も不十分になってしまうので高温期を維持することができなくなくて、すぐに生理がきてしまうんです。
そして、排卵誘発剤の最大のデメリットとも言える事が卵巣過剰刺激症候群という副作用です。
卵巣過剰刺激症候群が起きると卵胞が育ちすぎて卵巣が腫れてしまいます。
重症化すると腹水が溜まったり血液が濃縮したりして危険な状態に陥ることもあるので注意が必要です。
卵巣の中に卵胞がたくさんある人に起きる現象なんですが、特に20代の若い女性、多嚢胞性卵胞の人、AMHの値が高かった人は症状がでやすい傾向にあります。
対策としては、卵巣過剰刺激症候群が起きやすい薬hCG注射を避けたり、薬の量が多いロング法という方法は避けることが有効かもしれません。
本来、妊娠したくて不妊治療を受けていたのに、それが元で卵が育たなくなったり、卵巣が疲れてしまうという負の連鎖になることもあります。
排卵誘発剤の間違った使用は卵巣機能が弱まり、排卵誘発剤なしでは自力で卵胞が育たない、または薬を使っても卵胞が育たなくしまう事も不妊治療を始める前に知っておくと良いですね。
参考になれば嬉しいです。
iPhoneから送信
カテゴリ
- 妊活 (62)
- 妊活先生YouTube (28)
- 妊活のポイント (16)
- 不妊 (7)
- 腸内環境 (1)
- セックスレス (2)
- 会陰切開 (1)
- 帝王切開 (1)
- 陰陽論 (1)
- 腎 (2)
- 卵子 (1)
- 性欲 (1)
- 生理関係 (6)
- マタニティ (1)
- 逆子 (1)
- 産後の骨盤矯正 (3)
- 内臓と顔の関係 (1)
- エイジングケアと鍼灸 (1)
- 乾燥肌を防ぐ生活習慣 (1)
- 美容意識とお悩み (1)
- ホルモンと美容 (3)
- 40歳からのホルモンバランス (1)
- アディポネクチン (1)
- 活性酸素の体への影響 (1)
- 睡眠と美肌 (1)
- 糖質と体 (4)
- 糖化 (1)
- 内臓と美肌 (3)
- 肝臓 (1)
- 冷えと美容 (4)
- 美容と血液 (4)
- オ血と運動 (1)
- 陰陽の食材 (2)
- スキンケア (2)
- 食事と美肌 (4)
- 陰陽の食材 (2)
